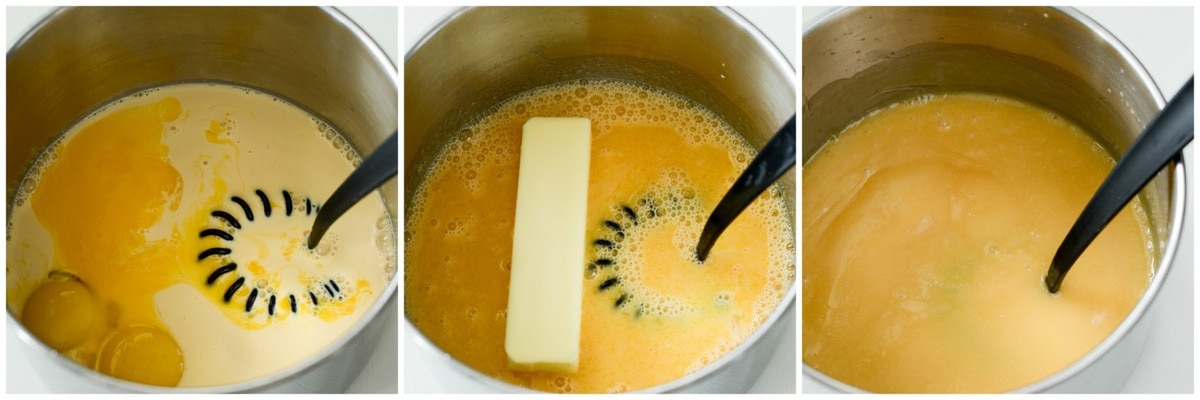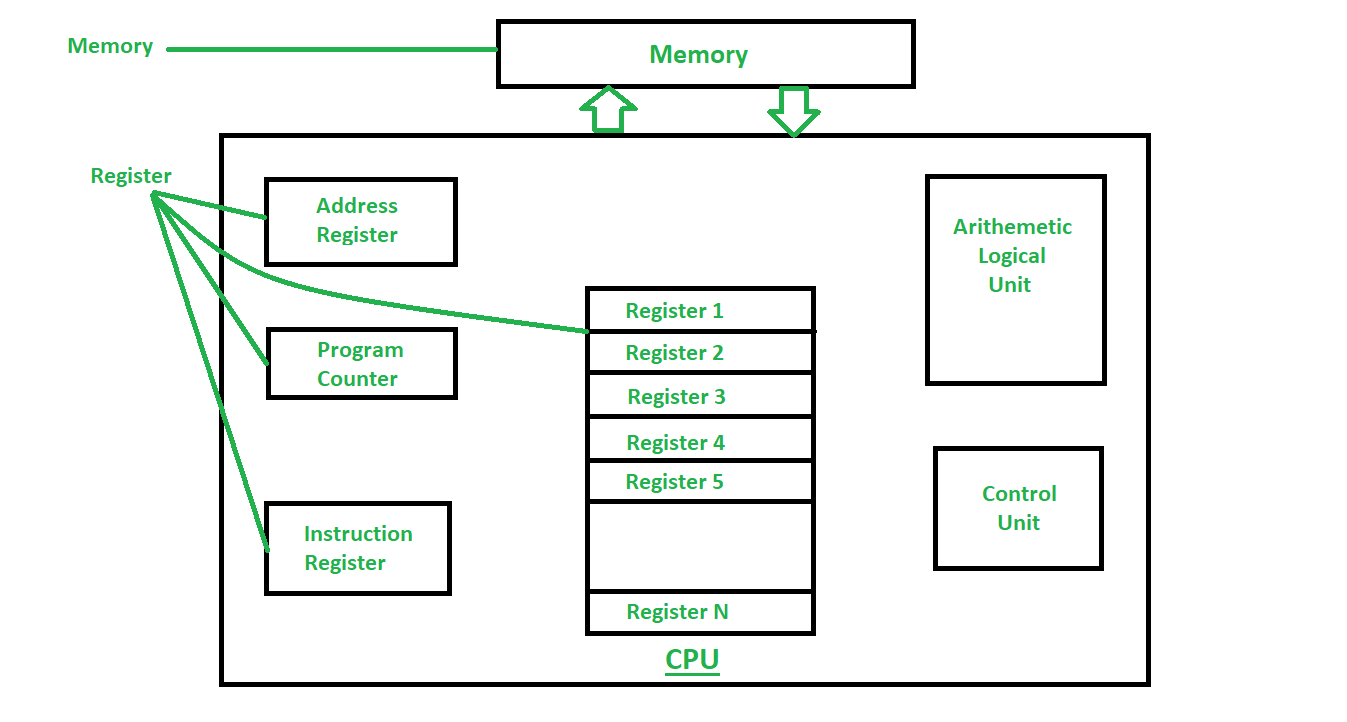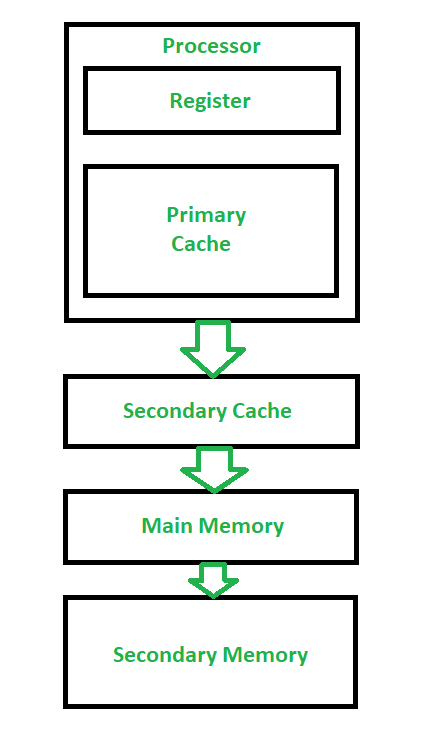Clavulina cristata
by Michael Kuo
Clavulina coralloidesとしても知られ、その白い色と「クリストート」(平たく、小さな点がいくつかある枝先)でフィールドで認識することができる、独特のサンゴ茸である。
最初の問題はClavulina rugosaで、典型的な形は非常に異なっているが(表面が荒く、枝数が少なく、枝先が鈍い)、Clavulina cristataと交雑して枝先を尖らせることがあるようである。
2つ目の問題は、別の菌、発熱菌のHelminthosphaeria clavariarumが日常的にClavulina cristataの根元から上に寄生し、グレーから黒に変化させることです。
ここまでのところ、2番目の問題は簡単に解読できそうですが、3番目の問題では、Clavulina cinerea が関係しています。この菌は、紫がかった灰色から灰色の色をし、枝先は鈍角から十字形に尖っています。 そこで問題だ。 それとも、Clavulina cristataがHelminthosphaeriaに侵されたものに過ぎないのでしょうか?
フィールドガイドの図版やインターネット上の写真を見てみると、Clavulina cristataに寄生されたものが「Clavulina cinerea」の数例と思われるが、図版標本の多くは枝がグレーから紫がかったグレー(濃いグレーや黒ではない)、基部付近が薄くなっており、上のグレーは基部を攻撃する寄生の影響ではないと示唆されている。 また、特徴的な子嚢がほとんどの写真で欠けている(低解像度でも子嚢は小さな点として見えることが多い、例として右のRichard Nadonの写真を拡大)。 しかし、乾燥させた後、すぐにキノコを紛失してしまったので、その正体を確かめるために顕微鏡的な特徴を評価することができないことを付け加えておきます。
しかしながら、Clavulina cinerea が Clavulina cristata に寄生していない(通常は)としても、後者の灰色の、しばしば破砕しない形態または「エコタイプ」を示しているだけかもしれません。 DNAの研究により、Clavulina cristataはHydnum repandumやCantharellus cibariusのようなシャントレルと並んで、他のほとんどのサンゴキノコから遠く離れていますが、Clavulina cristata、Clavulina rugosa、Clavulina cinereaが別種か同種の形態かという特定の問題については、これまで議論されてきませんでした。 ただし、ある研究(Pine and …