- 疾病部位
- 発生率
- 素因
- マクロ的特徴
- 自然史
- 臨床史臨床検査
- 特殊検査
- 予後
疾患部位
 注意欠陥多動性障害(ADHD)は多動を特徴とする神経行動学的症候群であります。 衝動性、不注意1-4 これらの症状はすべての人が時折経験するものですが、ADHDの患者さんでは深刻で持続的であるため、これらの人の正常な機能を妨げています1,2,4,5
注意欠陥多動性障害(ADHD)は多動を特徴とする神経行動学的症候群であります。 衝動性、不注意1-4 これらの症状はすべての人が時折経験するものですが、ADHDの患者さんでは深刻で持続的であるため、これらの人の正常な機能を妨げています1,2,4,5
ADHDを患う人は、しばしば社会環境、学問、職業環境でうまく機能できなくなることがあります。 1-4
就学前および就学初期の子どもの症状として最もよく知られていますが、ADHDの存在は、子どもの頃の症状の名残として、一部の大人でも認識されるようになってきています。 大人のADHDは1976年に初めて観察され、1987年に小児期の障害とは異なる状態として「精神障害の診断と統計マニュアル」に初めて含まれました6
発生率
ADHDの子どもの30~70%が大人になっても障害の症状を示し続けます。2控えめな有病率は、一般人口のほぼ20人に1人がADHDを持つと推定されています7
ADHDを持つ成人の割合は、1:4.0です。 米国の全国的な世帯調査であるNational Comorbidity Survey Replication(NCSR)では,18~44歳の成人におけるADHDの有病率は4.4%と推定されている7。オーストラリアの人口統計に基づくと,18~44歳のオーストラリア人36万人以上がADHDであると推定される82003年に,成人集団のうちADHDの刺激性医薬品を処方されたのは0.1%未満であった。 これは、成人1万人あたり7人の割合であり、この障害の重大な過小診断を浮き彫りにしています9
成人の状態は、男性と女性に等しく普及していることは興味深いことです10。しかし、刺激剤を服用している成人女性1人に対して、刺激剤を使用している成人男性は1.7人います9。
男女の寛解率に差があることを示す証拠はないため、女子のADHDの診断が不十分であることも反映しているかもしれません。

子どものADHDの詳細については、「子どものADHD」を参照。
素因
ADHD は幼児期に生じる持続的な状態である。 ADHDと診断された、あるいはADHDの症状を経験したことのある成人は、大人になってからもADHDである可能性が高い2。しかし、成人発症の証拠はない6。 以下は、成人期にも及ぶ可能性のある子どものADHDの素因をまとめたものである。
遺伝的要因
 ゲノムワイド連鎖研究からは、ADHDの遺伝性を支持する多くの証拠があり、平均一致率は0.76である。11 さらに、思春期に治まるケースに比べ成人期に持続するケースでは遺伝の影響がより強く関連していると考えられている。 ADHDの病因は遺伝的要素が強く、多くの遺伝子が関連していることは明らかであるが、神経伝達物質遺伝子の関与の程度は、特定のADHDのサブタイプでどれが示されるのかなど、まだほとんど分かっていない12
ゲノムワイド連鎖研究からは、ADHDの遺伝性を支持する多くの証拠があり、平均一致率は0.76である。11 さらに、思春期に治まるケースに比べ成人期に持続するケースでは遺伝の影響がより強く関連していると考えられている。 ADHDの病因は遺伝的要素が強く、多くの遺伝子が関連していることは明らかであるが、神経伝達物質遺伝子の関与の程度は、特定のADHDのサブタイプでどれが示されるのかなど、まだほとんど分かっていない12
ADHD は複雑な形質で、この障害と関連する特定の遺伝子を特定することを困難にしている。 例えば、最近の研究では、異なるADHDサブタイプに関連する遺伝子に注目し、特定のADHDサブタイプの特定の環境における特定の遺伝子間の相互作用がバリエーションを示すと考えられることが明らかにされている。 これまでのところ、ADHDに関連する遺伝子は215以上あるが、現在研究されているどの遺伝子変異も、障害の唯一の媒介因子として提示されていない11…


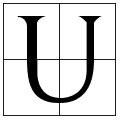 一部の歴史家が考えるのとは異なる。 スターリングラードは、一見したところ、もっと多くの価値を持っていた。 ヒトラーはスターリングラード内の膨大な資源を認識していたので、バルバロサ作戦の成績に対する彼の癇癪は正当化された。 スターリングラードの重要性の鍵は、1930年代に開発されたその工業力にある。 大きな国には、それに見合うだけの大きな需要がある。
一部の歴史家が考えるのとは異なる。 スターリングラードは、一見したところ、もっと多くの価値を持っていた。 ヒトラーはスターリングラード内の膨大な資源を認識していたので、バルバロサ作戦の成績に対する彼の癇癪は正当化された。 スターリングラードの重要性の鍵は、1930年代に開発されたその工業力にある。 大きな国には、それに見合うだけの大きな需要がある。  注意欠陥多動性障害(ADHD)は多動を特徴とする神経行動学的症候群であります。 衝動性、不注意1-4 これらの症状はすべての人が時折経験するものですが、ADHDの患者さんでは深刻で持続的であるため、これらの人の正常な機能を妨げています1,2,4,5
注意欠陥多動性障害(ADHD)は多動を特徴とする神経行動学的症候群であります。 衝動性、不注意1-4 これらの症状はすべての人が時折経験するものですが、ADHDの患者さんでは深刻で持続的であるため、これらの人の正常な機能を妨げています1,2,4,5
 ゲノムワイド連鎖研究からは、ADHDの遺伝性を支持する多くの証拠があり、平均一致率は0.76である。11 さらに、思春期に治まるケースに比べ成人期に持続するケースでは遺伝の影響がより強く関連していると考えられている。 ADHDの病因は遺伝的要素が強く、多くの遺伝子が関連していることは明らかであるが、神経伝達物質遺伝子の関与の程度は、特定のADHDのサブタイプでどれが示されるのかなど、まだほとんど分かっていない12
ゲノムワイド連鎖研究からは、ADHDの遺伝性を支持する多くの証拠があり、平均一致率は0.76である。11 さらに、思春期に治まるケースに比べ成人期に持続するケースでは遺伝の影響がより強く関連していると考えられている。 ADHDの病因は遺伝的要素が強く、多くの遺伝子が関連していることは明らかであるが、神経伝達物質遺伝子の関与の程度は、特定のADHDのサブタイプでどれが示されるのかなど、まだほとんど分かっていない12