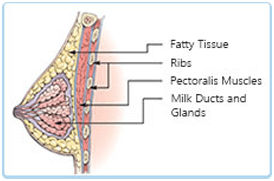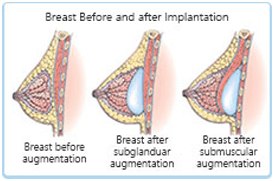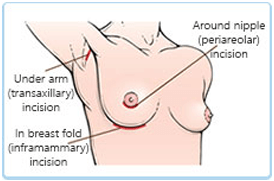サルマン・ラシュディのような巨大な作家の誇大宣伝と超現実主義、叙事詩的スケールと象形文字、テクストの花火と言葉の高揚、悪名と過剰な有名人性を、どうすれば1001字以内でとらえられるでしょうか。
もうひとつは、文化評論家のSukhdev Sandhuのように、大げさな表現に走ることでしょう。 真夜中までに彼がダンスフロアでお尻を振っていないマンハッタンの高級パーティーは失敗とみなされるかもしれない。 彼の小説は何十万部も売れ、『真夜中の子供たち』(1981年)は1994年にブッカー・オブ・ブッカーズに選ばれている。 (この印象的なリストに付け加えると、ラシュディの著作は、それ自体が小さな学術産業を生み出しており、彼の小説についてはすでに700以上の記事や章が書かれ、ラシュディの人生と作品に焦点を当てた長編の研究は30を下らないのです。 この大げさなアプローチの問題点は、サンドゥが指摘するように、「彼のフィクションに骨と歯ごたえを与えている歴史的、地理的な特殊性」を無視して、ラシュディに関する大雑把な一般化を招いてしまうことです。
この文脈では、ラシュディに関するより控えめでミクロな説明が賢明であるように思われます。 この作家の作品の形式的な可塑性を、グローバルなポストモダニズムではなく、インドの口承伝統の観点から説明したり、彼の映画への言及を、一般的で西洋的な「ボリウッド」の概念ではなく、1950年代のボンベイ映画の観点から説明したり、彼の作品を、「マジックリアリズム」「ポストコロニアリズム」といった包括的なラベルではなく、個別の文学的関心、ちょっとした強調のずれ、テーマ性の展開の観点から説明したりできるようなものでなければならない。 実際、ラシュディの処女作『グリムス』(1975年)が批評家から無視され続けているのは、その非典型的な性質と一般化に対する頑固な抵抗が一因であると言えるかもしれない。 この小説は、架空のカーフ島を舞台に、モダニズムと実存主義、アメリカン・インディアンとスーフィーの神話、寓話とSFを取り入れた不思議なスタイルのブレンドによって、フラッピング・イーグルの探求を描いている。 ラシュディの最初の小説は、ティモシー・ブレナンなどの批評家がその軽視を説明するように、地理的な想像力をしっかりと示している(にもかかわらず、またおそらくそのために)その後の彼の作品とは異なり、ある種の無限の可能性を持っている。 8610>
Midnight’s Children (1981), Shame (1983), The Satanic Verses (1988) はラシュディの現在までの代表作で、三部作とみなされることもある。 真夜中の子供たち』は、独立後のインドを描いたフィクションであり、サリーム・シナイという人物の人生を通して読み解く物語である。 独立の真夜中に生まれたサリームは、他の1001人の子供たちとともに、創造的かつ破壊的な方向へ導く不思議な力を授かった。
ラシュディによれば、『真夜中の子供たち』における歴史の偽造は、ロンドンに住む移住作家である彼自身が、子供の頃の記憶の不完全性を通して、想像上の故郷を捉えようとしていることの表れであった。 この移民というテーマは、次の2作の内容でますます中心的な位置を占めるようになる。 Shame』はパキスタンを描いたマジックリアリズム作品で、『真夜中の子供たち』と同様、家族の私的な物語を、国の公的・政治的歴史の薄っぺらな寓話的モデルとして用いている。 小説の舞台となる先祖代々の家は、ゴシック調で、地下にある迷宮のような空間で、窓は内側しか見えない。
『悪魔の詩』では、『恥』の主要な物語構造の中に断続的に噴出する分裂病的な移民の想像力が、テキスト全体を支配しているのである。 この小説は、飛行機へのテロ攻撃の余波で、海面からほぼ3万フィートの上空で始まる。 インド人の主人公サラディン・チャムチャとジブリール・ファリシュタが地上に転げ落ちると、彼らは悪魔と天使の姿に変容し始める。 この小説はイスラム教の歴史を描いているため、ラシュディにファトワーが発令されたことは有名な話である。
ファトワーの影で書かれたHaroun and the Sea of Stories(1990)は、大人のための童話であり、沈黙に対する物語の力を擁護する寓話的な作品である。 同様に、次作の『ムーア人の最後のため息』(1995年)は、『真夜中の子供たち』を思わせる部分もあるが、主にインドを舞台に、作者と「情事」を想起させる孤独と死のテーマを扱っている。 …